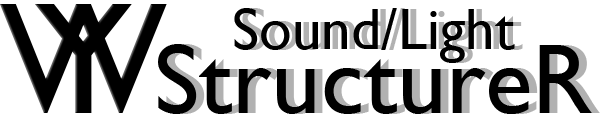「男はつらいよ」は、私の好きな映画の一つである。 といっても、全50作を網羅した熱狂的なファンというわけではない。見逃した作品もあれば、何回も繰り返し観た作品もあるという、付かず離れずの距離感だ。
この作品の魅力を一言で言えば、「マンネリズムの美学」に尽きる。 そしてそれこそが、私の提唱する「構造美」の本質へと繋がっている。
※「男はつらいよ」シリーズとは: 山田洋次原作・監督、渥美清主演。1xでいうところの「権威」すら超越した、日本の国民的映画シリーズである。テキ屋(露天商)を生業とする「フーテンの寅」こと車寅次郎が、故郷の葛飾柴又に戻っては騒動を起こし、旅先で出会ったマドンナに恋をしては失恋する……という様式美を四半世紀以上にわたって描き続け、世界最長の映画シリーズとしてギネス記録にも認定された。
揺るぎない「土台」と「柱」
この物語には、完璧に設計された「構造」がある。
葛飾柴又という強固な**「土台」。 そこに、車寅次郎という唯一無二の「主柱」**が立つ。 周囲を固めるのは、妹のさくら、その夫の博(ひろし)、裏の印刷工場のタコ社長、そして団子屋「くるまや」の叔父(おいちゃん)と叔母(おばちゃん)。
場所も、登場人物も、基本的には毎回同じだ。 冒頭はほぼ「寅次郎の奇想天外な夢」から始まり、旅先から柴又へ戻り、騒動が起きる……。この「型」は、恐ろしいほど徹底されている。
唯一の変数:マドンナという波紋
しかし、この物語には毎回一つだけ、決定的な「違い」が投入される。 それが、寅次郎が恋に落ちる**「マドンナ」**の存在だ。
土台も柱も梁(はり)も共通だが、この「マドンナ」という変数だけを差し替えることで、ストーリーは無限の変容を見せる。結末は常に「寅次郎の失恋と、再びの旅立ち」と決まっているにもかかわらず、私たちはそのプロセスに毎回新鮮な感動を覚える。
ここに、我々の表現活動における重要なヒントが隠されている。 写真であれ、音楽であれ、本質は同じなのだ。 強固な構造(土台)を持ち、取り巻く要素を固定した上で、そこに「一つだけ」違う要素を注ぎ込む。 その一点の差し替えが全体のパターンを変容させ、新たな構造美として結実するのである。
シンプルな構造が際立たせる「存在感」
約2時間の映画の中で、大きな筋書きは常に一定だ。しかし寅次郎の旅先は日本各地、時には海外(ウィーン)にまで及ぶ。 各地の風土を背景に、マドンナとの交流が描かれる。構造をあえてシンプルに固定しているからこそ、主演・渥美清という役者の圧倒的な存在感、そして細部(テクスチャー)の機微が、より一層鮮明に浮かび上がるのだ。
この偉大なシリーズは、1996年、主演の渥美清氏の死去によって幕を閉じた。 シリーズ後半は氏の体調もあり、甥の満男(みつお)の恋愛模様が中心となっていたが、結局は「寅次郎と満男のダブル失恋」という、見事な二重並列式構造として成立していた。
大船撮影所での記憶 ―― 山本直純氏との日々
余談だが、私にとってこのシリーズは特別な個人的記憶と結びついている。
シリーズ最終盤、そして後の特別編(『寅次郎ハイビスカスの花 特別篇』など)が制作されていた頃、私はこのシリーズの音楽を手がけた作曲家・山本直純氏のアシスタントを務めていた。 松竹の大船撮影所へ足を運び、あの独特の活気の中に身を置いた経験は、今も私の中に深く刻まれている。あの「くるまや」のセットの空気感、そして山本氏が紡ぎ出した、あのあまりにも有名な主題歌の旋律。それらすべてが、一つの巨大な「文化の構造体」であった。
「マンネリズム」という名の、強固な建築
もしあなたが、「最近マンネリズムに陥ってしまって……」と嘆いているのなら、こう伝えたい。 「大きく変える必要はない」と。
基礎からすべてを壊してしまえば、そこにあるのは建築の崩壊だけだ。 まずは、強固な構造を維持したまま、一つだけ要素を変えてみる。そして、その一点が全体にどのような変化を及ぼすのかを観察すればいい。
ただし、その「マンネリズム」が芸術として許されるためには条件がある。 それは、「誰にも壊せないほど強固で揺るぎない構造」を持っていること。 そして、その構造を彩る柱、梁、窓、テクスチャーの隅々にまで、最大限のこだわりを持って創り上げる気概があること。
寅さんが愛した柴又の街並みが、時代を超えても私たちの心に安らぎを与えるのは、そこに「変わらないことへの誇り」という、強固な構造が貫かれているからなのだ。